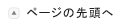![]()
研究の進め方
2012年7月12日
早稲田大学アジア太平洋研究科
松岡研究室
修士ゼミの進め方について
松岡ゼミでは以下の3種類のプレゼンテーションを行い、討論を行う
①ブックレビュー
②指定された教科書の章のレビュー
③自分の研究に関する発表
こうしたプレゼンテーションと討論を通じて、先行研究の選び方、リサーチクエスチョンの立て方、方法論の適切な選択、適用可能なデータソースの調査やケース選択の方法を学習しなければならない。
*PPTを作り、研究成果を発表することが目的ではなく、ゼミ生とのディスカッションや教授からのフィードバックによって自分の研究または、文献の内容を学術的に理解することが重要である。
①ブックレビュー & ②教科書の章のレビュー
【1学期目の学生】内容を要約することに主眼を置く。また、自分が理解した範囲を示し、疑問点を明示し、ゼミ内で議論することによって知識を深める。この一連の行動により、自分が興味を持っている分野の中から研究の対象を絞っていく。
【2学期目の学生】主にリサーチクエスチョンを考える。そのために、ブックレビューでは、特定領域の知識を広げていく必要がある。ブックレビューによって自分の研究に関する知識を付けていく中で、適した書籍や論文を見つける力を養っていくことができる。2学期目の学習を通して、リサーチ・プレゼンテーションの基礎を作る。
【3学期目の学生】ブックレビューを通して、リサーチクエスチョン(研究の問い)の立て方、その問いを追究するために必要な方法論やデータソースの選択の仕方を身に付ける。特に、関連した書籍や論文を探し出し、それに対して学術的な批評を行う必要がある。
③リサーチ・プレゼンテーション
3本から5本程度の先行研究(出来るだけ学術論文を選ぶ)を読み込み、その要点を把握した上で、リサーチクエスチョンを立て、それを追究するための方法論やデータの選び方についても考える。
*研究の動機(その研究を行おうとしたきっかけ)に終始しないように気を付ける。
研究報告の例
○ 修士Research Prop Sofyan Lury (Dec. 16, 2009): Effect of a Carbon Tax on Economy
○ 博士