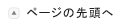![]()
松岡ゼミリーディングリスト
社会科学
1. 大来佐武郎(1987),『地球の未来を守るために』, 福武書店
2. 野中郁次郎・紺野登 (2003),『知識創造の方法論―ナレッジワーカーの作法』, 東洋経済新報社
3. 野中郁次郎(2020), 『知識創造企業(新装版)』, 東洋経済新報社
4. 藤本隆宏 (2003),『能力構築競争-日本の自動車産業はなぜ強いのか』, 中公新書
5. ロバート・D. パットナム(2001),『哲学する民主主義:伝統と改革の市民的構造』, NTT出版
6. ダグラスC. ノース (1994),『制度・制度変化・経済成果』, 晃洋書房
環境研究
1. 井村秀文・松岡俊二・下村恭民(2004),『環境と開発 (シリーズ国際開発)』, 日本評論社
2. 植田和弘・新沢秀則・岡敏弘(1997),『環境政策の経済学:理論と現実』, 日本評論社
3. ガレス ポーター、ジャネット・ウェルシュ ブラウン(1998),『入門 地球環境政治』, 有斐閣
4. 佐和隆光(2006),『環境経済・政策学の基礎知識』, 有斐閣
5. 武内和彦・住明正・植田和弘(2002),『環境学序説(1)』岩波書店
6. 日本の大気汚染経験検討委員会(1997), 『日本の大気汚染経験:持続可能な開発への挑戦』, ジャパンタイムズ
7. 宮本憲一(2014),『戦後日本公害史論』, 岩波新書
8. 大沼あゆみ・柘植隆宏(2021), 『環境経済学の第一歩』, 有斐閣
9.ニック・ハンレー、ジェイソン・ショグレン、ベン・ホワイト(2021), 『環境経済学入門』, 昭和堂
開発研究
1. アマルティア・セン(2002),『貧困の克服―アジア発展の鍵は何か』, 集英社新書
2. 北原淳・西沢信善(2004),『アジア経済論』, ミネルヴァ書房
3. 末廣昭(2000),『キャッチアップ型工業化論:アジア経済の奇跡と展望』, 名古屋大学出版会
4.Akira Suehiro(2008), Catch-Up Industrialization-The Trajectory and Prospects of East Asian Economi.Univ of Hawaii Pr; New版
5. マイケル・P. トダロ、ステファン・C. スミス(2004),『トダロとスミスの開発経済学』, 国際協力出版会
6. 松岡俊二・朽木昭文(2003),『アジ研トピックレポートNo.50:アジアにおける社会的環境管理能力の形成:ヨハネスブルク・サミット後の日本の環境ODA政策』, アジア経済研究所,90pp.
7. 松岡俊二 (2004),『国際開発研究:自立的発展へ向けた新たな挑戦』, 東洋経済新報社
8. Matsuoka, S. ed. (2007), Effective Environmental Management in Developing Countries: Assessing Social Capacity Development, Palgrave-Macmillan, London
9. 松岡俊二(2008), 「アフリカ開発とキャパシティ・ディベロップメント:ケニアの経済開発戦略と貿易政策を中心に」,吉田栄一(編)『アフリカ開発援助の新課題』, 日本貿易振興機構アジア経済研究所, pp.107-142.
10. ロバート・カッセン(1993),『援助は役立っているか:DOES AID WORK?』, 国際協力出版会
公共政策・評価研究
1. 足立幸男(1994),『公共政策学入門―民主主義と政策』, 有斐閣
2. D.E.リリエンソール(1950),『TVA―民主主義は進展する』, 岩波書店
3. 松岡俊二(2007),「第13章 環境評価」, 三好皓一(編),『評価論を学ぶ人のために』世界思想社, pp.224-241.
研究方法・論文作成
1. G. キング・R.O.コヘイン・ S.ヴァーバ・真渕勝(2004),『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論』, 勁草書房
2. P.G.ホーエル(1981),『初等統計学』, 培風館
3. 白砂堤津耶(2007),『例題で学ぶ初歩からの計量経済学 第2版』日本評論社
4. 木下是雄(1981),『理科系の作文技術』, 中公新書
5. マイケル・ポランニー (2003).『暗黙知の次元』筑摩文庫