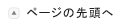![]()
北京研修
「大学院教育改革支援プログラム(大学院GP)」
「中国における持続可能な発展と日本の環境協力」
北京研修報告書について
本報告書は、文部科学省・大学院教育改革支援プログラム(大学院GP)に基づき、2009年2月19日(木)から2月24日(火)(5泊6日)に実施した「中国における持続可能な発展と日本の環境協力」をテーマとする北京研修の報告書である。研修には大学院生11名と教員1名(松岡)が参加した。
本研修は、海外の有力大学との合同ゼミナールなどを行うことにより、本学大学院生のプレゼンテーション能力や討論能力の向上を図り、議論に強い国際競争力のある大学院生の育成を目的として実施したものである。本研修は、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科・松岡研究室が中心となり、「中国における持続可能な発展と日本の環境協力」を統一テーマとして掲げ、北京市を対象に選定し、北京大学、北京師範大学、清華大学などの環境問題に関連する教授・大学院生との合同ゼミを企画するとともに、本テーマに関連する環境NGOや国際援助機関などの関連機関・組織のインタビュー調査や関連施設の視察も実施した。
本研修の企画においては、松岡研究室のAliceさん(D1)と池田さん(M1)がロジ、サブの両面において中心的に働き、中国・北京からの留学生・夏さん(M1)が協力した。それぞれの学生の努力・貢献に感謝します。また、北京大学のZhang教授、北京師範大学のTao教授、清華大学の張教授、常教授、温教授など北京の先生方にも感謝いたします。
日本と中国は長い歴史的交流の中で発展してきたが、19世紀後半から20世紀前半は極めて不幸な歴史を経てきた。西欧列強の植民地化の圧力への抵抗と近代化への努力の中で、日中は戦争や紛争を繰り返し、日本は傀儡国家・満州国を創設するなど中国に対して多大な被害を与えるとともに、日本自らも広島・長崎への原爆投下や沖縄戦などを経て、第二次大戦に敗北した。19世紀後半から20世紀前半の約50年間の日中関係は、お互いの信頼を大きく傷つけるものであった。
戦後、中国が中華人民共和国となり新たな国づくりを始め、日本は戦後復興から高度経済成長を経て新たな経済大国となった。1972年9月29日には日中国交回復が行われ、中国は1979年以降の改革開放のもとで急激な発展を遂げてきた。日本は国交回復後、特に中国の改革開放政策を支援するため総額3兆円を超える円借款や技術協力・無償資金協力を行ってきた。日本の中国へのこうしたODA(政府開発援助)供与は、中国の急速な経済成長につれ、1990年代以降、インフラ分野から次第に環境分野が大きな比重を占めるようになってきた。日中環境協力は1990年代後半から2000年代の前半におけるもっとも重要な援助イシューであった。
こうした日中環境協力は、中国における上下水道整備、森林保全、大気汚染・水質汚濁対策、日中友好環境保全センター、環境モデル都市事業(大連、重慶、貴陽)など様々な領域や形態で実施されてきたが、中国の汚染問題や自然環境問題は依然として深刻な状況にある。
一方、2008年の北京オリンピック開催を契機に、日本は中国への新たな円借款供与を終了し、今後の日中環境協力は技術協力(ODA)だけでなくNGOや企業など様々な民間アクター間の国際協力が重要となるなど、新たな展開が模索される転換点にあると言える。
他方、中国自身も新興援助国としてアジアやアフリカへの開発援助を積極的に展開するようになった。さらに地球温暖化による被害が目に見える形になりつつある中で、中国自身の気候政策の確立と国際的コミットメントが重要となってきている。
今後の日中環境協力は、単に日本と中国という2国間の環境問題だけでなく、日中が協力してアジアの環境、さらには世界の環境を守り、グローバル・サステイナビイティの実現のために日中が共に努力・協力・連携していくことが必要となっている。
今回の北京研修はこうした課題へアプローチするため、「中国における持続可能な発展と日本の環境協力」という統一テーマを掲げ、北京大学、精華大学、北京師範大学の大学院生と合同ゼミを行い、本研究科の院生たちも大いに刺激を受けたものと考える。参加した学生が今回の研修を契機に、一層自らの勉学・研究に励み、将来、地球環境の保全とグローバル・サステイナビリティ実現のため、世界の各分野で活躍することを願うものです。
最後に本プログラムの運営にあたられた山岡教授、川村教授、小林教授、村嶋教授および運営スタッフの山本さん、鄭さんに感謝の意を表します。
2009年4月16日
早稲田大学
大学院アジア太平洋研究科
教授 松岡 俊二